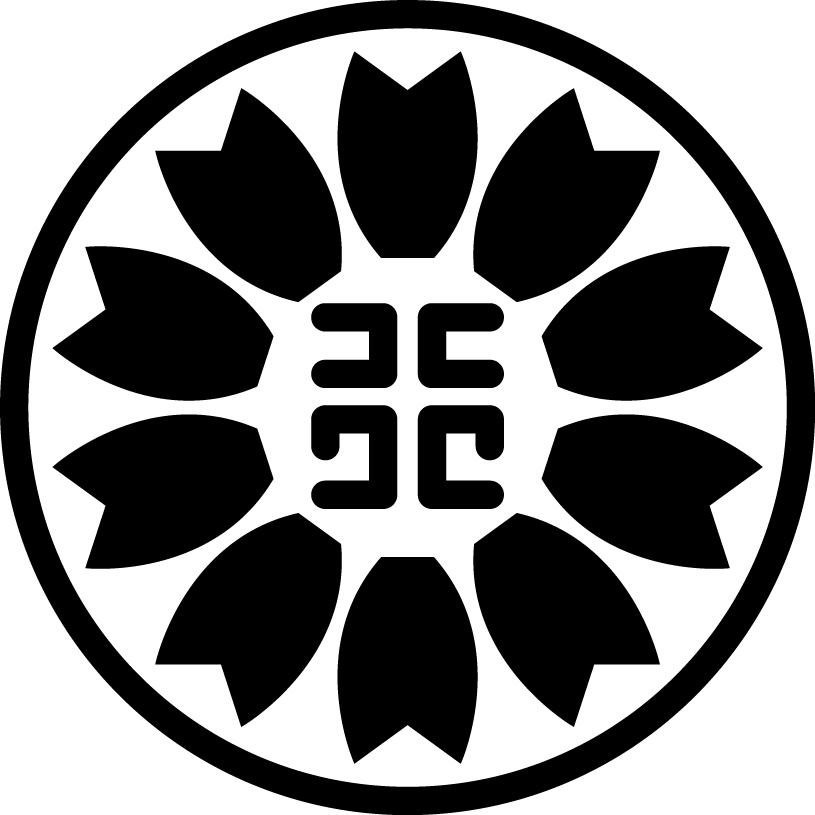生活保護申請の流れ
🏛 生活保護の申請の流れ(行政書士が同行する場合)
生活保護の申請は、「ただ申請書を書く」だけではなく、相談・調査・決定といういくつかのステップを通じて行われます。
それぞれの段階で、行政書士が同行すると安心できる場面が多いです。
① まずは福祉事務所に相談(事前相談)
住んでいる市区町村の「福祉事務所(生活保護担当課)」へ行き、困っている状況を相談します。ここで生活保護以外の制度(就労支援・貸付・医療費助成など)を紹介されることもあります。
行政書士が同行していれば、相談内容を整理してくれたり、職員にあなたの状況を正確に伝えてくれます。
📌 ポイント
「相談しただけでは申請したことになりません」。
正式に申請したい場合は、『申請書をください』と伝える必要があります。
② 申請書の提出
申請書は福祉事務所でもらえます。自分で記入するのが難しいときは、行政書士が代筆を手伝うことも可能です。
同時に、次のような書類の提出を求められます:
🧾 主な提出書類の例
①身分証(マイナンバーカード・保険証など)
②家賃の領収書や賃貸契約書
③通帳の写し(全口座)
④年金・障害年金の通知書
⑤医療費の領収書 など
📌 行政書士がいると安心な理由
書類に不備があると審査が遅れるため、行政書士が内容をチェックしてくれるとスムーズです。
③ 生活状況の調査(家庭訪問など)
申請後、福祉事務所の「ケースワーカー」が自宅を訪問し、生活の実態を確認します。
部屋の様子や家計の状況を見て、必要な支援内容を判断します。
不安な方は、行政書士が立ち会ってもかまいません。
📌 調査の目的
・本当に生活が困っているかを確認するため
・医療や仕事の状況、家族関係などを把握するため
④ 保護の可否(決定)
調査が終わると、通常2週間〜1か月ほどで結果が通知されます。「保護開始決定通知書」が届いたら、生活保護費の支給が始まります。
⑤ 保護の開始と生活支援
毎月、生活費(生活扶助・住宅扶助など)が支給されます。
ケースワーカーが定期的に訪問し、生活の相談に乗ってくれます。
働ける人は、就労支援や職業訓練を受けながら自立を目指します。
📌 行政書士の役割
・支給後も書類提出や更新手続きで困ったときに助言できる
・収入申告などのミスによる「返還」トラブルを防げる
💬 まとめ
生活保護の申請は、「相談→申請→調査→決定→支給」という5段階で進みます。書類の多さや説明の難しさから、不安や誤解が生まれやすい手続きです。だからこそ、行政書士が同行することで
手続きが正確に進む
不当な対応を防げる
安心して自分の生活再建に集中できる
といった大きなメリットがあります。
※生活保護申請時に必要なものは以下の通りです。
①世帯の預貯金7万円以下になっていること(役所はすべての金融機関と連携していますので急におろしてタンス預金などにしていると疑われます)②印鑑③記帳済みの通帳④生活保護申請書(書式は自由なので当事務所で作成したものを持参します)⑤マイナンバーカード(持っている方)⑥健康保険証⑦年金通帳(受けている方)⑧車検証(車を持っている方)⑨運転免許証(車を持っている方)⑩病院の診察券(現在かかっている方)⑪賃貸借契約書(持ち家の方は権利書)⑫過去3か月分の給与明細(働いている方)